1年ぶりに外で働き始めました。短期の学童保育で働き始めて2週間たった頃に書こうとしていた記事。(時間差になってしまいましたが)
40代、専業主婦として家にいた私が、久しぶりに「職場」に出て感じたことを記録しておこうと思います。

初めての出勤|戸惑いと緊張の一日
初日は、なにをしていいのか分からず、見よう見まねで行動。
主任の先生から指示をもらったり、周りを見ながら動いたりして、あっという間に一日が終わりました。
全くの未経験でしたし、仕事を始める前に一通りの説明などあるのかな?と思っていましたが、主任の先生から「見て覚えてね!分からないことはその都度聞いて貰えばいいからね!」と言われて少し戸惑いました。HSP気質ってそういうのがあまり得意では無い気がして。
夏休みということもあり、子どもたちは「通年通っている子」「夏休みだけの子」「8月から入ってきた子」などさまざま。
最初は名前も顔も覚えられず、ただただ必死でした。
メモを取ることも禁止されたので、帰宅して、その日に関わった子や覚えた子の名前と特徴など、携帯にメモしたりしていました。
子どもたちとの関わりで気づいたこと
初日から人懐っこくて、よくくっついてくる子がいました。
「かわいいなぁ」と思っていたら、その子は支援級に通っている子でした。
実際、このクラブにはそういった子が何人かいます。
方針は「どの子も平等に接すること」。
けれど、2週間働いてみて、私はそれが想像以上に難しいと感じました。
支援級の子たちはよく寄ってきてくれるので、自然と目がいってしまう。
もっと相手をしたいと思ってしまう。
一方で、他の子どもたちにも平等に接する必要がある…。
この経験から「大勢の子を相手にするよりも、少人数の子に寄り添う働き方のほうが合っているのかもしれない」と気づきました。
子供対応の難しさ
「同じ子ばかり相手をしてないでね!」
「先生、あっちの方も見てて」
など言われたり。
例えば、何人か遊べる程の机を囲んで子供たちが遊んでいました。
そこへ入りたい子がいて、他の子がちょっとずれてくれるとその子が入れたんです。
「◯◯ちゃんごめんね。ちょっとだけこっちにずれて貰えるかな?」
と、そのように対応していたら主任の先生に呼ばれて
「◯◯ちゃんが最初から座って遊んでたよね?そこに◯◯ちゃんが後から入りたいっていうのは、その子のわがままじゃないかな?最初からいた子は何で・・・って思うよね?先生の子がその子の立場だったら嫌じゃない?」
と注意を受けました。
正直私だったら、子供に「入れてあげな。」と言うと思いましたが、プロの対応はそうなんだ!と捉えました。
その頃から、自分の子供への対応が正しいのか不安になって、子供よりも「先生に見られている」というプレッシャーが凄かったんです。
先生」と呼ばれた喜び
そしてもうひとつ、働き始めてとても嬉しかったことがあります。
それは──子どもたちに「先生!」と呼ばれること。
今まで「先生」と呼ばれる立場になることがなかったので、最初にそう呼ばれたときは本当に嬉しくて、少し照れくさくて…。
でも、その呼びかけが今では毎日の原動力になっています。
出勤してすぐに「待ってたよ!」というように寄ってきてくれる子。「先生、先生!」と遊ぼうと誘ってくれたりして、心の底から「わたしはやっぱり子供が好きなんだ」と言うことを自覚しました。
まとめ|主婦の再出発は小さな一歩から
夏休みはまだ続きます。
子どもたちと関わる中で、もっといろんな気づきがあるはずです。
「私にとって、どんな働き方が合っているのか?」
その答えはまだ見えていません。
けれど、今こうして「先生」と呼ばれ、子どもたちと笑い合える毎日がある。
それだけで、きっと一歩ずつ進めているんだと思います。
同じように「働きたいけど一歩踏み出せない」と感じている方に、少しでも何か届けば嬉しいです。未経験のわたしでも、少しは社会の役に立てたのかな。と思っています。
。」次回は夏休み、仕事を1ヶ月半してみて思ったことなどを書きたいと思います
最後まで読んでくださってありがとうございました🌿

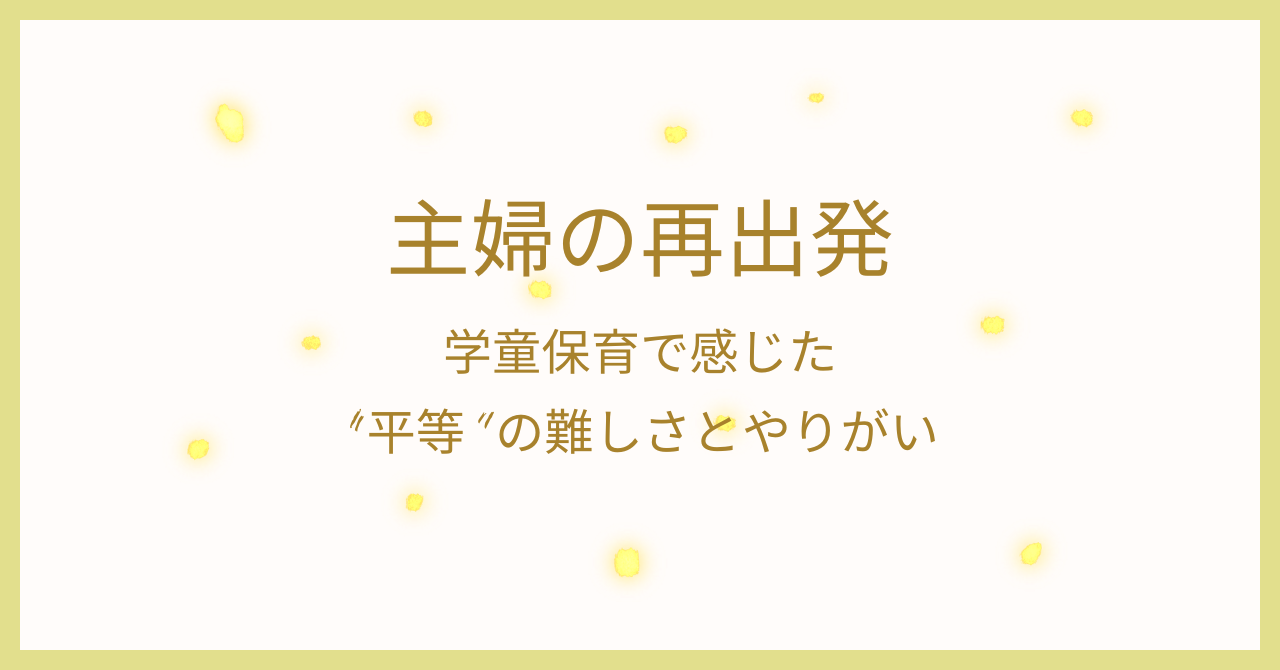
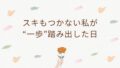
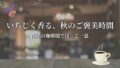
コメント